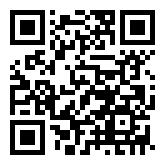日本の不動産・景気動向・税制
国税庁は7月1日、令和6(2024)年分の路線価を発表した。
標準宅地の評価基準額の対前年変動率は全国平均で2.3%上昇(前年:1.5%上昇)と3年連続で上昇した。
都道府県別では、上昇率5%の都道府県が、北海道・宮城県・東京都・福岡県・沖縄県(同1都道府県)。
上昇率5%未満は24都道府県(同24都道府県)、変動なしは2都道府県(同2都道府県)だった。
下落率5%未満は16都道府県(同20都道府県)に減少した。
都道府県庁所在都市の最高路線価1位は、東京都中央区銀座5丁目・銀座中央通り。1平方メートル当たり4,424万円(前年比3.6%上昇)で、39年連続でのトップとなった。
2位は大阪市北区角田町・御堂筋で、同2,024万円(同5.4%上昇)。
3位は横浜市西区南幸1丁目・横浜西口バスターミナル前通りで、同1,696万円(同1.0%上昇)となり、トップ3の順位に変動はなかった。
都市別では、上昇が37都市(前年:29都市)、横ばいが9都市(同13都市)、下落が1都市(同4都市)と、上昇傾向がみられる。
県庁所在地で最も上昇率が大きかったのは、千葉市中央区富士見2丁目千葉駅東口駅前広場の223万円(前年比:14.9%上昇)。
以下、さいたま市大宮区桜木町2丁目大宮駅西口駅前ロータリーの529万円(同11.4%上昇)、岡山市北区本町市役所筋の179万円(同9.1%上昇)が続いた。
(独)住宅金融支援機構は7月1日、取扱金融機関が提供する「フラット35」(買取型)の2024年7月の適用金利を発表した。
融資率9割以下・借入期間21年以上の金利は、年1.840%(前月比0.010%下降)~3.450%(同0.010%上昇)。取扱金融機関が提供する最も多い金利(最頻金利)は年1.840%(同0.010%下降)と、3ヵ月ぶりの下降となった。
融資率9割以下・借入期間20年以下の金利は年1.450%(同0.010%下降)~3.060%(同0.010%上昇)。最頻金利は1.450%(同0.010%下降)と、5ヵ月ぶりに下降。
長期優良住宅の取得を条件とする超長期住宅ローン「フラット50」の金利は、融資率9割以下・借入期間36年以上50年以下の金利は年1.940%~2.410%。最頻金利は1.940%。
(公財)不動産流通推進センターは6月20日、2024年5月の指定流通機構(レインズ)の活用状況を公表した。
新規登録件数は32万8,791件(前年同月比2.9%減)と、2ヵ月連続で減少した。成約報告件数は4万4,925件(同2.6%増)となり、13ヵ月連続の増加。総登録件数は84万8,370件(同0.2%増)と、14ヵ月連続の増加となった。
売り物件については、新規登録件数11万7,118件(同4.7%増)と、17ヵ月連続の増加。成約報告件数は1万5,053件(同8.3%増)となり、12ヵ月連続での増加となった。総登録件数は41万5,855件(同14.2%増)で、24ヵ月連続で増加した。
賃貸物件は、新規登録件数が21万1,673件(同6.7%減)となり、減少が27ヵ月続いている。成約報告件数は2万9,872件(同0.0%減)と、小幅ながら2ヵ月連続で減少した。総登録件数は43万2,515件(同10.4%減)で、21ヵ月連続で前年同月を下回った。
売り物件の取引態様別件数は新規登録のうち媒介契約が7万5,391件(同3.8%増)。内訳は専属専任媒介が1万1,368件(同7.0%増)、専任媒介が3万9,270件(同8.4%増)、一般媒介が2万4,753件(同3.9%減)となった。売り主は3万9,898件(同7.2%増)、代理は1,829件(同9.9%減)。
成約報告については、媒介契約は1万2,272件(同8.5%増)。そのうち専属専任媒介が2,462件(同6.6%増)、専任媒介が8,003件(同9.1%増)、一般媒介が1,807件(同8.6%増)となった。売り主は2,737件(同8.4%増)、代理は44件(同30.2%減)となった。
一般財団法人日本不動産研究所(JREI)は6月25日、2024年4月の「不動研住宅価格指数」(既存マンション)を公表した。
00年1月を100とした場合の指数は、首都圏総合が121.23ポイント(前月比0.81%上昇)と、4ヵ月連続で上昇した。前年同月比は4.57%の上昇。
地域別では、東京都が137.49ポイント(同0.78%上昇)と4ヵ月連続で上昇した。神奈川県は107.60ポイント(同1.88%上昇)と反転上昇。千葉県は87.99ポイント(同1.03%下落)と反転下落。埼玉県は92.95ポイント(同0.18%上昇)と、上昇に転じた。
(株)野村総合研究所(NRI)は6月13日、国内の2024~40年度の新設住宅着工戸数、23~40年のリフォーム市場規模、28~43年の空き家数と空き家率の推計・予測結果を発表した。
新設住宅着工戸数は、23年度の80万戸から、30年度77万戸、40年度58万戸と、減少していく見込み。利用関係別でも、40年度には持家15万戸(23年度:22万戸)、分譲住宅14万戸(同:24万戸)、貸家(給与住宅を含む)29万戸(同:35万戸)と、いずれも漸減する見込みとした。
また、昨今の工事原価の上昇が24年度は継続しない場合は、24年度の新設住宅着工戸数は86万戸、うち持家の新設住宅着工戸数が26万戸と見込まれるものの、工事原価の上昇が継続した場合は、24年度の新設住宅着工戸数は82万戸、うち持家は21万戸にとどまると予測している。
リフォーム市場規模は、今後もわずかながら成長を続け、40年には 8兆9,000億円に達する見込み(22年:約8兆1,000億円)。狭義のリフォーム(「住宅着工統計上『新築住宅』に計上される増築・改修工事」および「設備等の修繕維持費」)市場規模は、それより約1兆2,000億円小さい規模と見込んでいる。
一方、24年4月に発表された「住宅・土地統計調査」では23年の空き家率が13.8%と、同研究所が23年6月発表した予測値(17.4%)を下回った点については、「空き家の除却が進んだというよりはむしろ、世帯数増加に伴い居住世帯ありの住宅数が増加したため予測と実績の乖離が生じた」とした。
この世帯数増加と最新の「住宅・土地統計調査」を基に中長期の空き家数と空き家率を予測。43年には空き家率が約25%に上昇する見込みであるとした。
住宅の建て方別に空き家率の推移を見ると、長屋建+共同住宅の空き家率が減少している一方、一戸建では上昇した。
一戸建に住む割合が高い核家族等の居住世帯が増加しなかったためと推測している。
同研究所では、「単独世帯以外の世帯(核家族世帯等)数減少に伴い、一戸建の空き家数が増加することは、腐朽・破損ありの空き家数の増加につながる」とし、一戸建の腐朽・破損あり空き家数は43年には165万戸と23年(82万戸)の 倍以上となると予測。
「単独世帯から居住先として選ばれづらい一戸建は今後空き家率が急上昇し、それに伴い腐朽・破損ありの『危険な空き家』も急増が見込まれる」とした。
他のカテゴリーの記事も見てみる
- 不動産売買コンテンツ
- 不動産に関わる岡山の市況
- 不動産売買コンテンツ
- ご売却をご検討されている方
- 不動産売買コンテンツ
- つぶやき
- 不動産売買コンテンツ
- 不動産会社への訪問・現地見学について
- 不動産売買コンテンツ
- 引越しについて